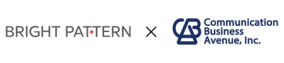コールセンター運営の形態は、インハウス(内製)とアウトソーシング(外注)の両方が選択肢として定着しつつあります。
「コールセンター白書2024」によると、完全にインハウスで運営している企業は全体の41%で、昨年度の43%とほぼ同水準を維持しています。
これは、多くの企業が自社に合った運営体制を模索しながら、それぞれの強みを活かす方法を選んでいることを示しています。
運営の自由度や柔軟性を重視して内製化を進める企業もあれば、専門性やコストの観点から外部リソースを活用する企業もあります。
いずれの運営体制にもメリットと課題がある中で、本記事では「内製化」の視点にフォーカスし、内製化のメリットとデメリット、課題へアプローチできるAIコンタクトセンターシステム「Bright Pattern(ブライトパターン)」について紹介していきます。
▼この記事が解決するお悩み▼
コールセンターを内製化したいけど、コストや人材確保が不安
外部委託先の状況が見えず、対応品質をコントロールできない
内製化すると繫忙期と閑散期で、オペレーターの人数調整が難しそう
コールセンター内製化のメリット

まずは、コールセンターを内製化する6つのメリットについて説明します。
VOCやナレッジの蓄積・共有ができる
チャットやFAQ、IVRなどにおいてAIの活用が進んでいることを背景に、自己解決率が向上し、電話によってVOCを直接収集する機会が減少してきました。一方で、VOCを活かしたパーソナライズや業務効率化の重要度は高まっています。また、有人対応に求められるスキルが多様化している現状も相まって、ナレッジの蓄積と活用は、顧客満足度向上に必要不可欠な要素となっています。
コールセンターが内製化できているなら、VOCやセンター運営のノウハウ、オペレータたちが蓄積するナレッジが、鮮度を維持したまま自社に蓄積していけるのです。顧客対応にまつわるトークスキルや、会社/製品・サービスの知識を確実に身つけて深めていけるので、人材を資本として捉え、企業価値向上にもつなげていけます。
迅速かつ柔軟な対応を実現できる
自己解決ツールの充実に伴い、コールセンターに寄せられる問い合わせは高度化・複雑化が進んでいます。必然的に、商品やサービスに関する専門的な知識や柔軟な顧客対応が求められる場面は増加します。
インハウス運営であれば、アウトソーシング運営にありがちな「委託元へのエスカレーション」という工数が発生しません。上長への確認が必要な場合でもすぐに対応することができるので、スピード感と柔軟さを両立させながら、顧客満足度の向上や信頼感の維持に貢献できます。
センター運営の透明性が期待できる
アウトソース運営には、運営上のさまざまな課題が存在します。
たとえば、「コールセンタージャパン2025年1月号」の調査によれば、業務委託するうえでの課題として、「自社のポリシーや文化を浸透させることが困難」(31.0%)、「業務がブラックボックス化して、実態がよくわからない」(23.9%)が挙げられています。いずれも、委託元でコントロールしきれるものではありません。
同紙では他にも「大手BPOベンダーでは人事ローテーションが比較的頻繁」であることや、「指揮命令権、人事権がなく、シェアード型などでは現場を直接、訪問することすら断るベンダーもいる」といった実態が指摘されています。
センターが内製化されている場合、運営課題をゼロにすることは難しくとも、管理・運営がすべて自社内でおこなわれることにより、今以上に高い透明性を期待できます。「内製化は難しくて失敗しやすい」と思われがちですが、実は必要とされるマネジメント知識やスキルはよりシンプルになるのです。
対応品質を維持向上しやすい
内製化に成功していると、コストをコントロールしながらサービス品質を維持向上していくことが可能です。とくに企業のポリシーや文化を正確に理解した上でサービスへと反映させやすいのは、コールセンターおよび企業にとって大きなメリットとなります。
たとえば、VOCの蓄積により、さらにリアルタイムかつ柔軟に顧客のニーズへ応えることができます。サービスや製品の品質向上や、新たな価値の提供が実現できるのです。
「コールセンタージャパン2025年1月号」によると、アウトソース運営に関する課題で最多回答だったのは「価格に見合った対応品質の維持」(54.9%)です。
低コストで高い品質を求める期待値とのギャップが指摘される結果となりました。プロフィットセンターとしての立場を確立したいコールセンターにとって、コストと品質の最適なバランスを保つことは必要不可欠な要素と言えます。
費用対効果の向上が見込める
インハウス運営については、コストカットが可能という見方と、反対にコストが増加するという2つの見方が存在します。各コールセンターが内製化を検討する際は、以下の選択が重要となってきます。
- 導入するコールセンターシステムの種類
- 完全インハウス型かアウトソースとのハイブリッド型か
これらの選択が重要な理由は、自社でコストをコントロールし、費用対効果を向上していけるためです。
セキュリティ面での安心度が高い
アウトソース運営をするからには、自社や顧客の情報を自社内でクローズすることはできません。そのため、情報漏洩のリスクをゼロにすることは不可能です。
とくに近年では、コールセンターにおけるAI活用が進んでいるので、高いセキュリティ力は企業全体の信頼や価値に直結します。内製化によってベースのセキュリティを高めつつ、AI活用で業務効率化を図っていくなら、顧客体験の向上やロイヤルティ獲得に寄与できます。
コールセンター内製化のデメリット

続いてコールセンター内製化のデメリットについても見ていきます。
コストと時間がかかる
コールセンターの内製化は、コストを削減できるとする意見がある一方で、かえってコストと時間がかかるという見方もあります。コールセンターを内製化する場合、アウトソーシング運営と比較して具体的に以下のような「コスト」と「時間」が必要になります。
【コスト】
- 電話設備への投資
- システムの購入・維持費
- オペレータの確保・教育費
- センター所在地の家賃
【時間】
- コールセンターの拠点選び
- 職場環境/周辺機器の準備
- オペレータの採用や教育
とはいえ、これらの「コスト」と「時間」は、コールセンターシステムの選択によってカットすることが可能です。
繁忙期・閑散期の人材コントロールが難しい
アウトソーシングの運営には、繁忙期・閑散期に合わせて人材をコントロールできるという強みがあります。一方でインハウス運営の場合、繁忙期と閑散期でオペレータの稼働状況を大きく調整していくことは困難です。
繁忙期に合わせてオペレータを雇用すると、閑散期には余剰人員が発生し、オペレータのモチベーション低下のリスクが上がります。閑散期に合わせて常に最低限の雇用にしていると、繁忙期に十分な対応ができなくなり、顧客満足度の低下やオペレータへの過剰な負荷による離職を引き起こしかねません。
とはいえ、座席数の増減がしやすいコールセンターシステムを活用することで、人材コントロールの最適化にアプローチしやすくなります。
内製化におすすめなAIコンタクトセンターシステム「Bright Pattern」

ここまでで、コールセンターの内製化に関する6つのメリットを説明してきました。自己解決ツールの発展と、それに伴う自己解決率の向上や、本格的なAI活用など、この数年で見られるようになった傾向に対して、多くの強みをもつのがインハウス運営です。
しかし、プロフィットセンターを目指すコールセンターにとって重大なデメリットがあることも、慢性的な人手不足や、業務の繁閑の差といった課題に対し、BPOの活用が効果的であることも事実です。
とはいえ、コールセンターシステムの選択によって、内製化に立ちはだかる壁を乗り越えることはできます。
ここからは、内製化のメリットを最大限享受しつつ、定常的な課題の解消を後押しするコールセンターシステム「Bright Pattern」(ブライトパターン)について紹介していきます。
繁閑の差に対応しやすいクラウド型
Bright Patternはクラウド型のコンタクトセンターシステムです。複数拠点をまたいだ人員配置や、オペレータのいる場所にとらわれないサポート体制を築けるので、座席数の増減に対応しやすく、繁閑の差に合わせてオペレータ数をコントロールしていけます。
また、Bright Patternには新機能としてAIによる「WFM(ワークフォースマネジメント)」が搭載されています。AIが業務データを分析したり、顧客の行動パターンや市場トレンドをもとに、問い合わせ量を予測分析したりできるので、最適な人員配置を実現しやすくなるのです。
〈具体的な効果例〉
- 人員コストの最大20%削減
- 予測精度は従来比15%向上
- SLA達成率の15−25%改善
- ピーク時の顧客待ち時間を最大40%削減
クラウド型で拡張性が高く、人員配置の最適化をサポートできるシステムを選ぶなら、繁忙期に合わせた増席も、突発的に生じる緊急対応に合わせたセンターの新規立ち上げも容易になります。
AIに完全対応
コールセンターにおけるAI活用は、今や採用難やオペレータ不足に対処していく上で必要不可欠な要素と言っても過言ではありません。Bright Patternには豊富なAI機能が搭載されています。Bright PatternのAI機能でできることについて、簡単にまとめていきます。
【Bright PatternのAI機能でできること】
- 対話の文字起こしと要約
- NLUとLLMを活用した高性能な対話型IVR
- パーソナライズされた自己解決を促進するAI IVR
- オペレータ向けナレッジサジェスト
- 注意が必要な対話をSVへアラート
- 正確な対応とコンプライアンス遵守をサポートするテレプロンプター
- 全チャネルの自動品質管理
- 顧客のインテント分析
- AIによるCSAT
- デジタルチャネルでのAI対応
- AIによる応対品質管理
- 品質管理の自動スコアリング
- 顧客の声に合わせて対応するAI IVR
- 応対品質を可視化するダッシュボード
モバイルアプリに対応
Bright PatternはiOSとAndroidのそれぞれにおいてモバイルアプリに対応しています。
アプリを活用すると、オフィスと個人のモバイル端末間の電話代や、電話機設置のコストカットが実現できます。また、場所に制限されないことで在宅ワークやハイブリッドコールセンターの実現・継続に貢献します。
くわえて、いつでもどこでも操作できる手軽さから、オペレータ以外のスタッフも顧客対応にあたることができ、社内全体が顧客接点として機能します。コストカットを図りつつ、部署や場所を越えた連携を可能とするのです。
圧倒的な費用対効果の高さ
Bright Patternはあらゆる大手カスタマーレビューサイトにて、導入期間、ROI、サポート品質、使いやすさ、顧客満足度の分野で高評価を獲得している、実績豊富なシステムです。
たとえば…
- アメリカ第二の大手銀行においては、2000人以上のオペレータをたった一週間で導入
- 大手モバイル通信プロバイダでは、95%の顧客満足度を実現
- 多言語展開のグローバルBPO企業では、オペレータトレーニング期間を86%削減
Bright PatternによるROI回収期間はおよそ9ヶ月で、運用コストは35%削減…と、圧倒的に高いROIを誇ります。
オンプレミス対応
医療や金融、公共インフラなど、機密性の高い情報を多く取り扱う業種においては、オンプレミス型でのセンター運用および内製化のニーズは依然として高いままです。
Bright Patternは、100%自社開発によるオンプレミス型にも対応しています。クラウド型と同じソフトウェアを使用しているので、クラウド型がアップデートされると、オンプレミス型も同時にアップデートされ、常に最新の機能を利用できるのです。
最後に
コールセンターの内製化には一定のハードルがあるものの、適切なシステムを選ぶことで、その壁は乗り越えることが可能です。Bright Patternのような柔軟性と拡張性を備えたシステムを活用すれば、部分的あるいは段階的な内製化が現実的な選択肢となるはずです。
まずは、自社にとって「どこまで内製化できそうか」をイメージしてみるところから始めるのはいかがでしょうか。