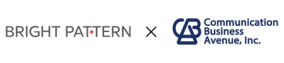お客さまとオペレータが存在してこそ成り立つコールセンターは、今なお労働集約型の構造から抜け出すのが難しい業界です。慢性化する人手不足により、接続品質の低下や、ストレスとそれによって引き起こされる離職といった課題も依然として解消できていません。
これらの連鎖した課題へアプローチするカギとして注目されているのが、「ワークフォースマネジメント」です。
この記事では、改めてワークフォースマネジメントに取り組むべき理由とメリット、Bright Pattern Contact Center(ブライトパターンコンタクトセンター)の機能である「WFM(ワークフォースマネジメント)」機能の詳細について解説していきます。ぜひコールセンターの経営戦略の一助として参考にしてください。
【この記事が解決するお悩み】
継続的に人員が不足している中、人材育成、カスハラ対策、応答品質の維持、業務効率化、セキュリティ強化…取り組まなければいけないことが山積している
オペレータやSVにかかっている業務負担が心配
ワークフォースマネジメントとは

ワークフォースマネジメントとは、主にサービスの質を落とさず、人員の効率的な配置や最適化を図るマネジメント手法のことです。必要な人員数の予測・シフトや勤怠管理・従業員のスキルマネジメントなどが含まれます。略して、WFM(work force management)と表記されることがあります。
ワークフォースマネジメントは、接続品質・応対品質を高水準に保ち、顧客満足や従業員満足の向上を目指す上では欠かせない「コールセンター運営の基本」となる部分です。
今ワークフォースマネジメントが重要な4つの理由

ワークフォースマネジメントは、決して目新しいマネジメント手法ではありません。そのため、すでに取り組んだ上で以下のようなジレンマを抱えるコールセンターは少なくありません。
- 「人手不足なので、ワークフォースマネジメントに取り組んでオペレータを最適化したいのに、そのための人的・時間的余裕がない」
- 「必要な人員数の予測やシフト作成などは、担当するSVへの負担が大きい上、予測値からのズレや突発的な呼量の増減などが発生するので、ワークフォースマネジメントの定期的な見直しは難しい」
しかし、今あるAI活用の流れを受けて、ワークフォースマネジメントも新たなフェーズへ突入しています。
くわえて、コールセンターを取り巻く環境もさまざまに変化しています。そこで、今一度コールセンター運営の基本に立ち返ってみましょう。まず、今改めてワークフォースマネジメントが重要と言える4つの背景的要素について考えます。
① オムニチャネル化によるワークフォースマネジメントの複雑化
現在多くの企業が、多様化する顧客ニーズへの対応と生産性向上を目的に、チャットやボイスボットを活用し始めています。とはいえ、これまで電話で受けていた問い合わせ数が、チャットやボイスボットにそっくりそのまま分散・シフトするわけではありません。
つまり、チャネルを拡充した分だけ、チャネルごとの業務量・ピーク予測が必要になるということです。
そのため、場当たり的なオムニチャネル化は、かえってワークフォースマネジメントを複雑化させるリスクがあります。
人手不足によってリソースが限られている今、オムニチャネルに対応しながら接続品質と対応品質を高水準で維持し、顧客体験を向上させていくことは容易ではありません。
② AI活用によるワークフォースマネジメントの理想と現実
「コールセンター白書2024」の調査結果を見ると、多くのセンターがExcelで呼量予測をしている現状がわかります。
- 過去の呼量データと現場のマネジメントがExcelなどを利用して行っている:54%
- 過去の呼量データとビジネス概況(会員数・売り上げなど)をもとに、現場のマネジメントがExcelなどを利用して行っている:22%
これらによる予測精度について、32%が「予測値±10%以内だが、時間帯によっては大きく外れることがある」と回答しています。
予測値を大きく外れた時間が長引いたり、大幅なズレが頻繁に起こったりする場合、その度に顧客満足度の低下あるいはコストの浪費が生じている可能性が高いので、楽観視できない結果です。
同書の調査で、「(コールセンターにおいて)生成AIの活用成果で期待したい点」には、「SVやセンター長などマネジメント職の自動化や省力化」(21.2%)が上がっている一方、呼量予測について「WFMシステムを導入しシステム化」していると回答したのはわずか6%でした。
AIによるSV業務支援という「理想」に注目が集まる一方で、AI活用によるワークフォースマネジメントは浸透していないという「現実」がうかがえる結果となっています。
③ 人手不足にも関わらず山積する業務課題
慢性的に人手が不足している中、人材育成、カスタマーハラスメント対策、応答品質の維持、業務効率化、セキュリティ強化など、コールセンターがすぐにでも取り組まなければいけない課題が山積しています。
その上、オペレータやSVの業務・精神負担を考慮しながら、離職防止にも策を講じなければいけません。
いずれも優先度の高い課題であるため、オペレータを効率的に配置して最適化を図り、各課題へ迅速にアプローチすることが重要です。
④ 接続品質の停滞または低下傾向
コールセンターにおいて「接続品質」は顧客満足度に直結する上、もっとも不満が発生しやすい要素です。
「コールセンタージャパン2025年10月号」の「コールセンター利用者調査2025」によれば、「つながりやすさ」は業種間の差が大きく見られるとされており、接続品質を昨年から維持できている業界もあれば、改善している業界もあります。
たとえば、同特集には「クレジットカード業界は昨年の41.0%から34.5%と接続品質が低下しているようだ」と書かれています。このように、人手不足のあおりを受けている業種も見受けられます。
ワークフォースマネジメント×AIでさらに効率化

改めて今ワークフォースマネジメントに取り組むべき4つの背景について解説しました。従来の人手によるワークフォースマネジメントでは、かえってリソースを圧迫させてしまったり、予測値からのズレに対応するのが難しかったりといった課題がありました。
しかし、現在は最新のAI活用によるワークフォースマネジメントが浸透しつつあります。
Bright Pattern Contact Centerが搭載している「WFM(ワークフォースマネジメント)」機能を例にして見てみましょう。
「WFM(ワークフォースマネジメント)」機能では、AIによる過去の業務データの分析、顧客の行動パターンや市場トレンドをもとにした問い合わせ量の予測分析などを行えます。例外的な事象の判別も可能なので、より正確な分析や予測が可能です。
「WFM(ワークフォースマネジメント)」には下記のような基本機能が付いています。
- 通話量予測(フォーキャスティング)
- 要員計画(スタッフプランニング)
- シフト作成(スケジューリング)
- 勤怠/タイムオフ管理(アテンダンス/休暇管理)
- リアルタイム管理(リアルタイムモニタリング)
- パフォーマンス分析(レポーティング)
- アラート通知機能
「WFM(ワークフォースマネジメント)」の導入効果として、以下のような効果が上がっています。
〈効果例〉
- 人員コストの最大20%削減
- 予測精度は従来比15%向上
- SLA達成率の15−25%改善
- ピーク時の顧客待ち時間を最大40%削減
最新のAIが上記のような効果を実現してくれるので、「ワークフォースマネジメントへ取り組むために人員や時間を割かなければいけず、その余裕がない」というジレンマの解消が見込めます。
ワークフォースマネジメントに取り組むメリット

最後に、AI活用によって精度や効率が向上したワークフォースマネジメントに取り組むメリットについて整理しましょう。
コスト削減と品質・顧客満足の向上の実現
AI活用によるワークフォースマネジメントで人員配置が最適化されると、最小限の人員で最大限のパフォーマンスを実現できます。
「最小限のオペレータ数で業務を行いたいものの、イレギュラーな呼量増加への対応を考えていくと結局のところ余剰人員が発生してしまう。余剰人員を回避して人件費を減らしつつ、オペレータに負担をかけずに品質や顧客満足度を維持していきたい」といった願いにアプローチできます。
オペレータの人数や配置が最適であれば、お客さまのコール待ち時間を最小にでき、それに伴って応答率や稼働効率が向上します。必然的に接続品質が高くなり、顧客満足度の向上にも直結します。
オペレータが働きやすい環境の整備
AIの分析によって、従来よりも正確な呼量予測やオペレータのシフト作成・配置が可能になります。そのため、オペレータ一人ひとりの細かな勤務希望や事情を反映しやすくなり、新たに以下のようなメリットが生まれます。
- 勤務希望の反映漏れリスク低下
- 先々の予定が予測できる
- 急なシフト変更や過剰な負担を最小限に抑制
これらのメリットは、育児・介護・在宅など多様な働き方にも対応していけるので、「働きやすいコールセンター」の実現につながります。企業のイメージアップや従業員満足度向上により、離職予防やリファラル採用の強化にもつながるでしょう。
複数拠点のリソースと複数チャネルの一元管理
複数拠点をもつセンターにとっては、一元管理による柔軟な人員活用が大きなメリットとなります。
拠点をまたいだリソース管理が実現すると、とくに人員が不足しているチームにオペレーターを派遣したり、余剰人員を研修に充てたりすることができます。各拠点という絞られた視点ではなく、センター全体としての広い視点で人員を活用することが可能です。
オムニチャネル化が進む現在においては、「拠点」だけでなく「チャネル」をまたいだ視点での管理も重要です。
AIによってチャネル別の対応件数やピーク予測ができると、複数チャネルをまたいだ人員の最適化に対応できます。チャネル間の業務量バランスや、オペレータのスキルに応じたルーティングができることで、より効率的かつ柔軟な運用が実現します。
SV/リーダーの負担軽減と業務の属人化の解消
従来のExcelを使った手作業によるワークフォースマネジメントから、AIによる自動管理へシフトするなら、SVの定常的な負荷を大幅にカットしつつ、業務の効率化と最適化が図れます。
AIによって大量のデータを瞬時に分析し、最適な予測とシフト作成が可能となるからです。呼量予測時に処理できるデータ量が多ければ、予測値からの大幅なズレの軽減・解消も期待できます。
AIによる業務支援・代替が実現できると、SVの時間的余裕の創出につながります。これにより、現代のSV/リーダーたちに求められる「時代の変化に合わせた改革推進力」「サービス設計力」「業務改善の施策提案力」などの成長支援や、戦略業務へ注力できるでしょう。
結果として、SVの離職要因とされる「業務過多」を解決したり、「SVのための教育・研修」を増やしたりしていくこともできます。
最後に
人手不足が慢性化している時代に、改めてワークフォースマネジメントに立ち返って基本を強化することは、単なる「業務効率化」にとどまりません。コールセンターひいては企業全体の経営戦略に直結し、その他の業務課題へ積極的にアプローチしていく上で強みとなるからです。
最新のAIによる最適なワークフォースマネジメントを体験してみませんか。